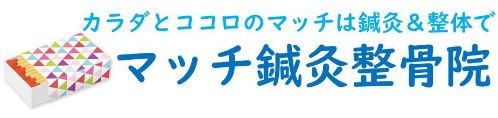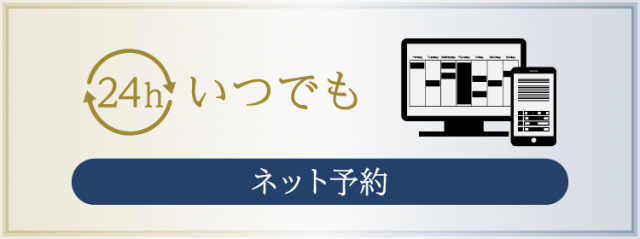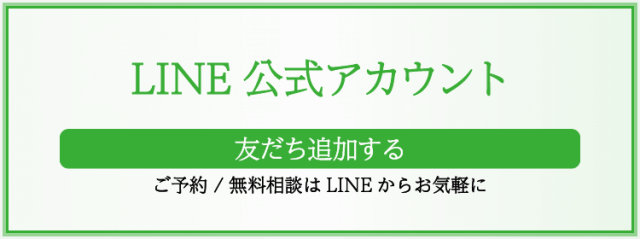サーカディアンリズムと睡眠の深い関係
「夜になっても眠れない」
「朝起きるのがつらい」
そんな悩みを抱えていませんか?
現代人の多くが感じている睡眠の問題、その根本には体内時計と言われている「サーカディアンリズム(概日リズム)」の乱れが潜んでいる可能性があります。
今回は、睡眠障害や不眠の改善に大きく関係するサーカディアンリズムについて、わかりやすく解説します。

マッチ鍼灸整骨院
院長 町村 祐輔
• 鍼灸師・柔道整復師
• 夏の甲子園出場経験有
国家資格取得後、整形外科・消化器外科のリハビリ室長を経験、オリンピックトレーナーの元でトレーナーを経験した後、札幌大通円山エリアにマッチ鍼灸整骨院を開業14年目を迎える
臨床歴は22年、鍼灸や整体による手技療法の可能性を日々探求しています。
1. サーカディアンリズムとは?
あなたは規則正しい生活はできていますか?
夜勤などがあり難しい方もいらっしゃると思いますが、一般的には一日のリズムは大まかに決まっていると思います。
それが乱れる事で様々な問題が起きてきます。
1-1. 体内に備わる24時間のリズム
サーカディアンリズムとは、生まれた時から持っている約24時間周期の生理的なリズムのことです。
夜行性の動物もいますが、人間は「朝になると目が覚めて、夜になると眠くなる」のが、自然なリズムです。
このリズムは、脳の「視交叉上核(しこうさじょうかく)」という部分でコントロールされており体内時計の中枢として機能しています。
【サーカディアンリズムを乱す原因】
- 目から入る光刺激
- 食事
- 運動 など
これらの過度な刺激が長期的に続くと自然なサーカディアンリズムが乱れ体に不調をきたす場合があります。
1-2. 恒常性(ホメオスタシス)との違い
睡眠障害や質の良い睡眠を考える際にサーカディアンリズムと混同されやすいのが、「恒常性(ホメオスタシス)」です。
睡眠における恒常性(ホメオスタシス)とは疲れたら眠るといったシンプルなものです。
つまり、活動中に酷使した脳や体を睡眠により休ませる事が出来ればおのずと体は整ってきます。
活動量に対する睡眠の質と量により脳や体に疲労を溜めない工夫が必要です。
- サーカディアンリズム
1日周期で規則正しく眠気や覚醒をコントロールするしくみ - 睡眠における恒常性(ホメオスタシス)
疲れたから脳や体を休ませる機能
この2つの機能がバランスよく働くことで、私たちはスムーズに眠り、気持ちよく目覚めることができるのです。
2. サーカディアンリズムの乱れが引き起こす不調
ここまではサーカディアンリズムの機能についてお話してきましたが、乱れると体にどのような影響を及ぼすのでしょうか?
2-1. 睡眠障害
夜型の生活や不規則な睡眠時間、スマートフォンの使用によるブルーライトの影響などはサーカディアンリズムが乱れる原因となり、睡眠の質は著しく低下します。
その影響は
- 不眠
- 早朝覚醒
- 中途覚醒
を引き起こし、慢性的にサーカディアンリズムを無視した生活を続けていると上記の頻度が増えていき
- 夜になっても眠れない
- 朝早く目が覚めてしまう
- 眠りが浅くてすぐに目が覚める
などの症状があらわれてきます。
2-2. 日中のだるさや集中力の低下
体内時計がずれることは睡眠障害だけでなく体に様々な影響及ぼします。
- 日中の眠気や倦怠感
- 仕事や授業の成績低下
- イライラしやすくなる
- 食欲を抑えられない
- 風邪をひきやすくなる
など、サーカディアンリズムの乱れによる体調不良が起きる場合があります。
3. 体内時計のズレが「肥満」や「糖尿病」にも関係?
最近の興味深い情報として、近年の研究では、サーカディアンリズムの乱れが単なる睡眠の問題やそれに伴いうつ病などの精神障害だけでなく
- 肥満
- 高血圧
- 糖尿病
などの生活習慣病の発症リスクを高めることがわかってきました。
特に夜寝る前の食事は、本来内臓を休ませるべき時間に胃腸などの臓器を働かせなければならず本来の体内リズムと消化のタイミングがずれていきます。その結果、血糖値が上がりやすくなるというデータもあります。
睡眠中の体を動かさない基礎代謝の低い時間に体内に食べ物がある事により脂肪が付きやすく肥満の原因にもなります。
サーカディアンリズムのズレは眠れない、倦怠感だけではなく病気のリスクが高くなるという事を頭に入れておきましょう!
睡眠不足になると思考の低下や作業効率が落ちたり、試合中の集中力が続かなかったり・・・ そんな時、糖分を摂取することで作業効率や集中力が向上した経験はありませんか? そんなウマい経験を一度したら最後、寝不足対策には糖分補給で万事解[…]
4. サーカディアンリズムを整える方法
あなた自身のサーカディアンリズムは人間の本能的なリズムなので変える事は難しいです。
なので自分自身のサーカディアンリズムを知る事が大切です。
自分のサーカディアンリズムとずれた生活が定着してしまうとそれが自分のリズムと錯覚してしまうことで体調は悪化していきます。
よいリズムの中に自分の生活習慣をあてはめる事により、体調も精神状態も安定してきます。
中には夜型の方がいらっしゃるので、そのような方は昼夜逆で考えていただけたらと思います。
ずれたリズムを取り戻すためには鍼灸と整体、段階的な生活習慣の見直し、運動で解消されることが多いです。
しかし、不安な方は一度病院を受診して検査を受けてからご来院下さい。
ここでは日常動作を変える事でサーカディアンリズムを整える方法について紹介していきます。
4-1. 朝日を浴びる
サーカディアンリズムは朝のカーテンを開けるところから始まります。
外はもう明るいのに部屋が真っ暗だサーカディアンリズムのスイッチを押すことができません。その為、活動モードになれずいつまでのベッドから起きる事ができなくなってしまいます。
そのよう状態を避けるためにはまず、朝目が覚めたらすぐに太陽の光を浴びることです。
朝の光は脳が「朝だ」と認識し、覚醒スイッチが入ります。
スイッチをオンにした後に明るい所で活動していれば15〜16時間後に段階的にスイッチがオフになっていき自然と眠くなる時間がやってきます。
その時にベッドに入れる環境を整える事が大切です。
4-2. 食事時間も規則正しく
不眠に悩む方は食事が不規則の方も多いです。
この食事が体内時計に影響し睡眠障害を招いていることもあります。
連日の飲み会で遅い時間に脂っこいものを沢山たべたり、夜遅くにスナック菓子を食べてしまったなどの暴飲暴食で不眠を招くことはありますが、
食事を食べる時間が不規則なことによりサーカディアンリズムの乱れを招くことも考えられます。
朝・昼・晩の3食(2食の方も)を毎日できるだけ同じ時間に摂ることでリズムが整いやすくなります。
「今日は12時にご飯食べれたけど昨日は忙しすぎて昼食が15時だった」
みたいなことにならない日々のスケジュール管理が必要です。
しっかり眠るために「食事」について意識したことはありますか? 「朝から体が重たい」 「夜中に胃がムカムカして起きてしまう」 「日中眠たい」 そんな悩みを抱えている方は「食事」に原因があるかもしれません。 私たち[…]
4-3. 就寝前のスマホ・PCを控える
近年問題になっているスマホやタブレットから発せられるブルーライト、この光は脳を昼間と錯覚させ睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を妨げます。
睡眠前、ベッドにはいって作業や動画をしている方は要注意!
日中の活動効率の減少を招いている可能性が高いです。
寝る1時間前は画面を見ない習慣をつけましょう。
4-4. 寝る・起きる時間を一定に
休日前の夜更かしや飲み会、深夜の締めのラーメンで楽しんだ後、翌日は昼まで爆睡、このような不規則な生活はサーカディアンリズムを乱す大きな原因です。
たまには良いと思いますが、睡眠に問題を抱えている方がこのような生活をしていたら治る事はありません。
倦怠感や無気力状態になり症状は悪化する一方です。
飲み会や深夜の暴飲暴食は控え、平日・休日問わず、毎日起床、睡眠を同じ時間にすることを意識しましょう。
「また眠れなかった…」そんな夜を何度もくり返していませんか? 布団に入っても目が冴えてなかなか眠れない。 ようやく寝たと思ったら、夜中に何度も目が覚める。 朝やっとの思いで目を覚ますもスッキリしない。 […]
5. 時差ボケとサーカディアンリズム
海外旅行に行かれる方が覚えておいてほしいのは、「時差ボケ」
これもサーカディアンリズムのズレが原因です。
たとえば日本からアメリカ西海岸へ行くと、体はまだ日本時間に沿って動いているため、現地の夜になっても目が冴えて眠れなくなるのです。
「時差ぼけ」による症状は不眠やだけでなく
- 眠気
- 倦怠感
- 食欲不振
- 頭痛
- イライラ
このように、私たちの体内時計は非常にデリケートで、ほんの数時間のずれることでも体の不調を引き起こしてしまうのです。
6. 体内時計についてのまとめ
サーカディアンリズム(体内時計)を意識した生活を送ることは、不眠に悩む方だけでなく健康に生活していく為に必要な事でもあり、
質の良い睡眠を得る為に必要な事です。
現代社会にはサーカディアンリズムを乱す要因が昔より増えました。
- 暗い寝室のベッドの中でも動画が見れるスマートフォン
- 深夜に小腹が空いたら夜中でも営業しているコンビニ
- 電子レンジやお湯を注げばすぐにできる冷凍食品やカップ麺
これらの便利な手段ではありますがその反面、健康被害を及ぼすリスクがあるという事を理解して使用すべきです。
睡眠による問題を抱えている方は睡眠導入剤などを飲んでいる方もいると思います。
薬を否定するつもりはありませんが、本来に人間に備わっている「睡眠」という機能が働かなくなっているという事は異常な事です。
薬を飲まなくても寝れる習慣をみにつける事が大切です。
その一つとしてサーカディアンリズムを乱す習慣を見直す必要があります。
【サーカディアンリズムを整える方法】
- 朝日を浴びる事
- 就寝前1時間前のスマホの使用制限
- 起床・就寝時間の一定
など、
つまり、規則正しい生活をすることで体内時計は驚くほど整います。
鍼灸や整体で歪みや自律神経を整える事はその生活習慣の見直しによる不眠対策の効果を高めます。
不眠や睡眠障害に悩む方こそは自分の「体内時計」に目を向けてみてください。
それが、自然と眠れる毎日への第一歩です!
マッチ鍼灸整骨院で睡眠障害・不眠を解消!
 当院では、睡眠の問題に特化した鍼灸整体施術で早期改善を目指します。
当院では、睡眠の問題に特化した鍼灸整体施術で早期改善を目指します。
- 鍼灸治療: 経絡を整え身体の内側から血流を促進、痛みや痺れを改善します。
- 整体・骨盤矯正: 骨盤や腰椎の歪みを整え、身体の外側から痛みや痺れを改善します。
- 再発予防トレーニング: 快適に眠れる体つくりをサポートします
- オーダーメイドの治療プラン: 一人ひとりの症状や生活スタイルに合わせた治療プランを提案します。
起床、就寝時に倦怠感や寝れないといった場合は早めの対応が肝心です。 「我慢できるから大丈夫」と思っている状態はずでに身体の状態はかなり悪くなっています。
少しでも気になる症状がある場合は、お気軽にご相談ください。
マッチ鍼灸整骨院が、症状の改善から予防まで全力でサポートします!
早めの治療で、快適な毎日を取り戻しましょう!