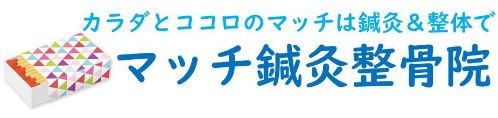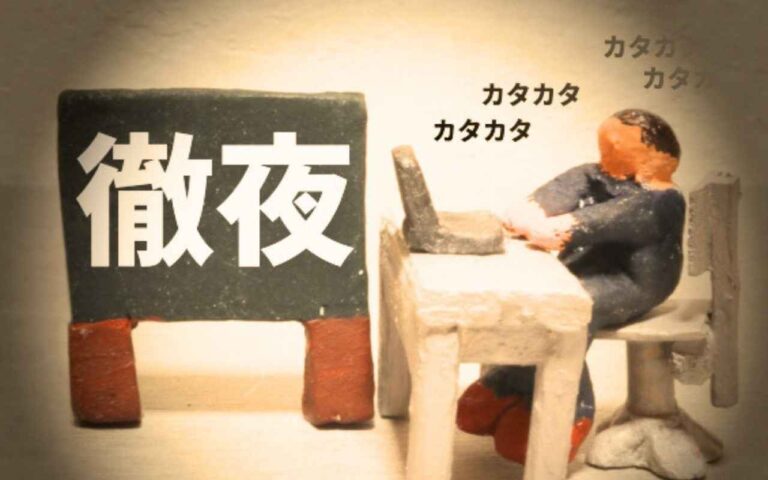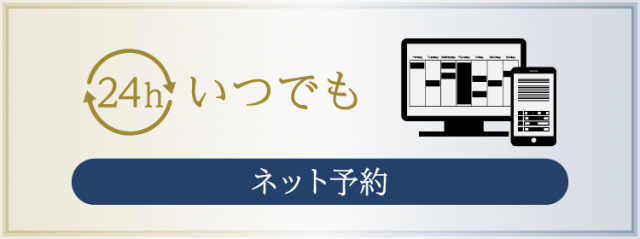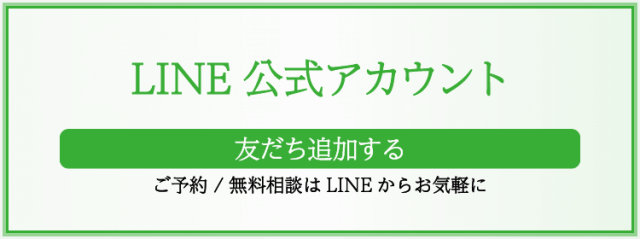- 「朝、全然起きられない」
- 「起床した後もなかな動けない、朝が苦手」
- 「夜になると元気が出てくる」
自分の体質が夜型かも?と感じたことはありませんか?
実はその体質は、サーカディアンリズム(概日リズム)という体内時計の性質と深く関係しているのです。
本来、人間には日を浴びると覚醒し暗くなると眠くなるといった一定の睡眠と覚醒のリズムがあります。
ですが、全ての人間が朝方かというとそうではありません。
今回は、朝型・夜型の違いやそれぞれのメリット・デメリット、そして夜型の人の健康への影響についてわかりやすく解説します。
夜型タイプが知っておくべき睡眠と健康の話
自分は夜型と思っている方は本当に夜型なのでしょうか?
- 夜中にゲームに集中できる
- 勉強も夜中にする方が効率がよい
- 薄暗い方が本を読み進める事ができる
という理由だけで夜型と判断している方、それは間違いです。
そのタイプの思い込みにより健康を害している可能性もあります。
本当にあなたは夜型なのか?
生活のリズムをもう一度確認してみましょう!
1.サーカディアンリズムとは?
サーカディアンリズムとは、24時間周期で体の生理機能を調整する「体内時計」のことです。
脳の視交叉上核(しこうさじょうかく)という部位によりコントロールされており、
睡眠・覚醒・体温・ホルモン分泌などを調整しています。
このリズムは光や食事、運動によっても影響を受けます。
日常生活では特に光の影響が大きいとされています。
特にブルーライトの影響は近年深刻な問題になりつつあります。
サーカディアンリズムと睡眠の深い関係 「夜になっても眠れない」 「朝起きるのがつらい」 そんな悩みを抱えていませんか? 現代人の多くが感じている睡眠の問題、その根本には体内時計と言われている「サーカディアンリズム(概日リズム[…]
2.なぜ朝型と夜型が存在するのか?
人間は朝日を浴びて起床し、夜暗くなると眠くなる、多くの方はシンプルな脳の仕組みになっているはずなのですが人間も動物、一般的なリズムとは違う人がいてもおかしくないと思う。
朝方と夜型が存在する理由は、
- 遺伝子レベルでの違い(先天的)
- 生活スタイルの変化(後天的)
によることが分かってきています。
2-1. 遺伝子によるクロノタイプの違い
人それぞれの睡眠タイプは、「クロノタイプ」と呼ばれる遺伝的な傾向で決まっていることが近年の研究で分かってきました。
クロノタイプは、朝型・中間型・夜型に分類され、それぞれが違ったタイミングで眠気を感じ、パフォーマンスが高まります。
- 朝型
朝に活動力が高く、夜は早めに眠くなる - 夜型
夜に集中力が高まり、朝は起きづらい
VoCEでクロノタイプの簡易診断を行っているので
「体内時計タイプを一度はチェックしてみてはいかがでしょうか?」
2-2. 社会的な影響と生活スタイルの変化
もともと遺伝的に夜型でなくても、夜勤や夜更かしの習慣、スマートフォンの使用などによって、後天的に夜型になってしまう人も多くいます。
近年パソコンによる長時間作業やスマホに普及により、社会的時差ボケ(ソーシャル・ジェットラグ)が問題視されるようになってきています。
実際、動物の世界でも夜行性の動物と日中活動する動物がいるように人間も夜型と朝方がいても別に不思議なことではないと思います。
- 朝起きて仕事をするのが辛い方は夜中に働く仕事の方が向いている
- 夜勤が辛い方は健康に害を及ぼす前に仕事を変えるべき
会社の立場的な問題や家族の問題はあると思いますが、一度働き方を見直してみてはいかがでしょうか?
3. 夜型生活のリスクとデメリット
3-1. 健康への悪影響
夜型体質と診断された方も夜型の生活を続けると、以下のような健康リスクが高まるとされています
- 睡眠の質の低下
- 肥満や糖尿病のリスク増加
- 高血圧や心血管疾患のリスク
- うつ症状や不安感の増大
人間が身体を休めるべき夜間に活動を続けることは夜型の方にとっては正常な行動なのですが、太陽の光を浴びる時間は減少します。
そのため、ホルモン分泌や代謝に乱れが生じることは避けられないのでその結果、身体に問題が起こる場合があります。
3-2. 社会生活とのズレ
夜型の人は、朝9時ごろ開始される一般的な社会のリズムと合わず、遅刻や集中力の低下による仕事のミスが多い傾向にあります。
その為上司から指摘をされたり、取引先からクレームが入ったりすることで精神的な問題を抱えやすくなります。
夜寝る前のスマホの見過ぎや夜更かしによるものであれば生活習慣の見直しで解決されますが、
元々夜型の方脳内のサーカディアンリズムが一般の方とずれている為、改善は難しいです。
元々夜型の方は、夜勤や夜間の仕事に転職するなどした方が能力が発揮できると考えますし、一般の方にはできない能力だと思います。
しかし、夜型の生活は朝日や紫外線を浴びる機会が減るため
【夜型タイプの健康のリスク】
- 体内時計の調整がうまくいかない
- ビタミンDの生成が減少で骨密度の低下骨
- 免疫力の低下
をおこすリスクがあるという事は頭に入れておいてください。
4. 夜型にもメリットはある?
夜型の人は絶対朝方に変えるべきなのか?
そうではありません。
夜型の方にもメリットはあります。
- 夜間の集中力・創造性が高い
- 静かな時間に作業ができる
- 独自のリズムで動ける自由さ
アーティストやフリーランスなど、時間に縛られないライフスタイルには夜型が合う場合もあります。
実際、夜型の歌手や芸術家が素晴らしい作品を残しているのも事実です。
しかし、それは睡眠のサイクルが夜に集中できるということであって内臓などの身体の機能が一般的なサイクルかもしれません。
そのような場合、アイディアや作品に集中できるからといって長期的に夜型を続けることは、健康を損なうリスクを高めるため注意が必要です。
5. 睡眠不足が招く深刻な影響
「ちょっとぐらい寝なくても大丈夫!」そう思っていませんか?
夜型生活が続き睡眠時間が不足すると、以下のような影響が出てきます
- 記憶力・集中力の低下
- 情緒不安定・イライラ
- 肥満
- 免疫力の低下
- 肌荒れ・老化の加速
このような脳への影響は睡眠時間を沢山寝たからといってリカバリーできないことも分かっています。
つまり、週末に寝だめをしても、平日の慢性的な睡眠不足を帳消しにすることはできないのです。
睡眠不足になると思考の低下や作業効率が落ちたり、試合中の集中力が続かなかったり・・・ そんな時、糖分を摂取することで作業効率や集中力が向上した経験はありませんか? そんなウマい経験を一度したら最後、寝不足対策には糖分補給で万事解[…]
6. サーカディアンリズムを整えて朝型に近づけるには?
夜型の生活が自分にあっていると思っている方はその生活スタイルで問題ないと思いますが、朝方にしたいけど長年しみついた生活スタイルが抜けずに夜型生活を続けている方は健康面を考えても朝方にした方が良いと思います。
ここでは朝方に近づける方法について紹介していきます。
6-1. 朝日を浴びて体内時計をリセット
朝の太陽光は、体内時計をリセットする最大の鍵です。
起きてすぐカーテンを開けて光を浴びるだけでも、サーカディアンリズムは整いやすくなります。
6-2. スマホ・PCの使用を控える
夜遅くまでのスマートフォンやパソコンの使用は睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌を妨げ、体が昼間だと錯覚し寝つきが悪くなります。
寝る1〜2時間前には画面から離れましょう。
6-3. 寝る・起きる時間を固定する
体内時計は「習慣」によって整えられます。就寝・起床時間を毎日同じにすることが、朝型への第一歩です。
7. あなたはフクロウ型とヒバリ型
人類の進化の過程でも、大きく分けると昼に活動する「ヒバリ型」と夜に活動する「フクロウ型」が存在したとされています。
フクロウ型(夜型)の特徴
【特徴】
-
夕方から夜になるほど元気が出てくる
-
朝の目覚めが悪く、午前中の仕事効率が悪い
-
深夜から早朝に最も集中力が高まり、創造力が高まる傾向
-
睡眠時間が遅く、起床時間も遅くなりがち
-
社会の一般的な生活リズムとズレやすい(=社会的時差ボケ)
フクロウ型の健康被害
-
睡眠不足になりやすく、慢性的な疲労感
-
肥満、糖尿病、うつ症状、心血管疾患のリスクが高まりやすい
-
社会的に「怠けている」と誤解されやすい
ヒバリ型(朝型)の特徴
-
朝早く目覚まし無しで自然に目が覚める
-
午前中に集中力や仕事効率が高くなる
-
夜は早く眠くなり、日が沈む頃にはリラックスモードに入る
-
一般的な社会のリズム(9時〜17時)をキープしている
健康面では
-
規則的な生活のリズムが保たれていて、睡眠の質が高い
-
欲求の抑制ができるので、うつ病やメタボリック症候群のリスクが低い傾向
-
体内リズムの安定により、ホルモンバランスが整いやすい
なぜ違いがあるの?
この違いは遺伝的要因(クロノタイプ)に加えて
年齢・生活環境・仕事スタイルなども影響します。
-
思春期〜20代
夜型傾向が強くなりやすい -
30代以降〜高齢者
徐々に朝型に変化していく人が多い
つまり、若い時は夜型だろうが朝型だろうがどちらでもよくて遅くまで遊んでい翌日昼間で寝ていてもさほど体へのダメージはありません。
なぜなら、その生活が自分のタイプに合っていなかったとしても体が元気で順応できるからです。
しかし、30代になると、頑張っても2次会まで、翌日昼間で寝てもまだ体が重い、そのようなイベントが連日続けば倦怠感による無気力、体重も増え風邪もひきやすくなり・・・良いことはありません。
この年齢や生活環境による朝方への変化は自分自身を守る為の変化ともいえます。
8.夜型タイプが知っておくべき事まとめ
生まれ持った夜型体質の方もいると思いますが、近年は長時間のパソコン作業や寝る前のスマホを見る事で寝つきが悪くなり夜型になっている方も多くいます。
生物の進化の過程で朝型・夜型の生き物がいるように人間にも夜型と朝型が存在しますのどちらが良いという事ではありません。
最も重要なのは「質の高い睡眠をしっかり確保すること」です。
不規則な生活が続き体内リズムが崩れると、睡眠の質は低下していきます。
質の悪い睡眠が長く続けば体に何らかの健康被害が表れてきます。
まずは自分の生活リズムを見直しが大切です。
夜型体質で体調に不安のある方は朝型の習慣を少しずつ取り入れていく事が大切です。
なぜなら、睡眠は翌日の疲労を回復するだけではなく、
- 健康
- 美容
- 集中力
- 感情の安定
すべての土台になるからです。
急に全ての習慣を変える必要なありません。
今日からできる小さな習慣が、将来の大きな健康につながります。
眠れない、朝がつらいと感じている方こそ、「サーカディアンリズム」(体内時計)と自分の体質に向き合ってみてください。
仕事が忙しくて寝る時間が遅くなる、スマホゲームに夢中になり毎日寝不足、健康に良くないと分かっていてもしてしまう夜更かしですが睡眠は人間の生命維持に必要な手段だという事を軽視している傾向にあります。 この記事をお読み頂き […]
マッチ鍼灸整骨院で睡眠障害・不眠を解消!
 当院では、睡眠の問題に特化した鍼灸整体施術で早期改善を目指します。
当院では、睡眠の問題に特化した鍼灸整体施術で早期改善を目指します。
- 鍼灸治療: 経絡を整え身体の内側から血流を促進、痛みや痺れを改善します。
- 整体・骨盤矯正: 骨盤や腰椎の歪みを整え、身体の外側から痛みや痺れを改善します。
- 再発予防トレーニング: 快適に眠れる体つくりをサポートします
- オーダーメイドの治療プラン: 一人ひとりの症状や生活スタイルに合わせた治療プランを提案します。
起床、就寝時に倦怠感や寝れないといった場合は早めの対応が肝心です。 「我慢できるから大丈夫」と思っている状態はずでに身体の状態はかなり悪くなっています。
少しでも気になる症状がある場合は、お気軽にご相談ください。
マッチ鍼灸整骨院が、症状の改善から予防まで全力でサポートします!
早めの治療で、快適な毎日を取り戻しましょう!