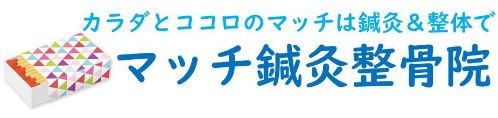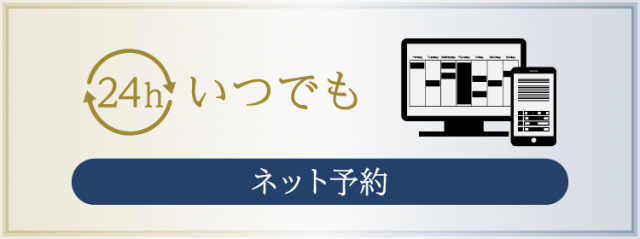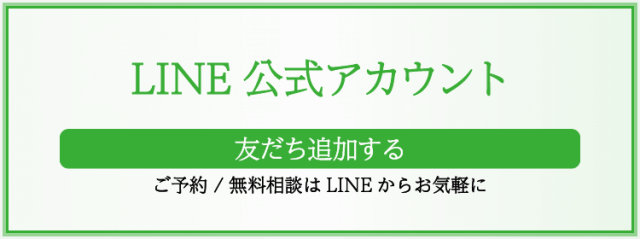「布団が冷たくてなかなか寝つけない」
「夜中暑くて何度も目が覚めてしまう」
そんなお悩みありませんか?
それはもしかすると体温が関係しているかもしれません。
睡眠と体温には深い関係があるのです。
この記事では、体温の仕組みと睡眠の関係、そしてぐっすり眠るためにできる体温調節のコツをご紹介します。
1.睡眠と体温調節の関係とは?
私たちの体温には「深部体温(体の中の温度)」と「皮膚温(体の表面の温度)」があります。
このうち、睡眠に大きく関係するのが深部体温です。
ポイントは深部体温の低下
日中は高く保たれている深部体温ですが、夜になると自然と下がり始めます。
この「深部体温が下がる」タイミングで眠気が訪れるのです。
たとえば、手足がぽかぽかしてくると眠くなることってありますよね。
これは、皮膚温が上昇し体が火照った感じがすることもあると思いますが、この現象は体の熱がうまく外へ逃げて、深部体温が下がる際におきる現象なのです。
つまり、
【眠気を誘う体温の条件】
- 「深部体温が下がること」
- 「皮膚温が上がること」
これが、質の高い眠りにとってとても大切なのです。
2.睡眠の質が落ちる体温トラブルとは?
では、どんなときにこの深部温度と皮膚温度のバランスが乱れてしまうのでしょうか?
以下のような原因が考えられます。
2-1.冷え性
手足が冷たくてなかなか眠れない人は熱をつくる事が出来ないのではなく、熱が体外に放出されにくい状態です。
その結果、深部体温が下がらないことで足先、指先がなかなか温まらず、寝つきが悪くなります。
2-2.ストレスや自律神経の乱れ
ストレスが続くと交感神経が優位になり、血管が細くなることで血流が悪くなります。
その結果、脳が覚醒状態となりやすく体温の上昇を招き睡眠に悪影響を与えます。
2-3.暑すぎる・寒すぎる寝室
寝室の温度や湿度が快適でないと、皮膚温の調整がうまくいかずに結果的に深部体温も下がりにくくなります。
- 暑すぎる場合
皮膚温が元々高くなりすぎている為、深部体温を下げる事ができない - 寒すぎる場合
部屋の温度が低いことで皮膚体温が下がっている為、深部体温で皮膚温を上げても室温の影響で皮膚温が下がってしまう
3.質の高い睡眠を得るための体温調節対策
ここまでは「深部体温」と「皮膚温」のバランスが睡眠に重要だという事をお話してきましたが、ここからはぐっすり眠るための具体的な「体温調節のコツ」をご紹介します。
【睡眠の質を高める体温調節対策8選】
- 起床時に朝日を浴びる
質の良い睡眠を得る為に夜の過ごし方が大切だと思っている方が多いと思いますが、起きた時が一番大事!
起床時に朝日を浴びることで体内時計がリセットされ体温調節が正常化されます。 - 就寝90分前の入浴
40℃前後のお湯に15分ほど入ることで、深部体温が上がります。
その後、髪を乾かしたり、歯を磨くなどの就寝準備の時間で体温が自然に下がっていきベッドに入るころに入眠するのに丁度よ体温になっているため寝つきが良くなります。※寝る直前のお風呂は逆に寝つきを悪くするので寝つきが悪い方はシャワーの方が良いです。 - 手足を温める
湯船につかる時間が無い方や湯船につかった後も手足が冷たく入眠しにくい方はこちらの方法がオススメです。
湯たんぽや足湯、レッグウォーマーなどで手足を温めると熱の放出が促され、深部体温が下がりやすくなります。※圧縮性の靴下タイツは浮腫みには良いと言われていますが睡眠の向上にはなりませんので注意! - 軽いストレッチや深呼吸
寝る前に軽くストレッチをしたり、ヨガや深呼吸をしてリラックスすることは、副交感神経が優位になり、血管が広がる為流れが穏やかになる事で寝つきを良くすることができます。 - 寝具・パジャマの見直し
季節に応じで吸湿性・通気性に優れた素材を選ぶことで暑くなりすぎたり寒くなりすぎる事を防ぐことで体温調節をおこないます。
冷感や速乾性、発熱素材のインナーも多数販売されているので、それらと組み合わせる事で睡眠の質は向上します。 - 寝室の温度と湿度を整える
理想の寝室環境は以下の通り夏:26~28℃
冬:16~20℃
湿度:50%前後エアコンや加湿器を上手に使って、快適な空間をつくりましょう。 - 食事は寝る2〜3時間前に
就寝直前の食事は消化の為に深部体温を上げてしまう事や、内臓を働かす為に血液が集中し脳に送られる血液や酸素の量が減ってしまうので寝つきを悪くする原因になります。
夕食はなるべく寝る2〜3時間前に済ませるのが理想です。 - 適度な運動
適度な運動は血液循環を促進し、体温調節をスムーズにします。
寝る前の激しい運動は交感神経を高め逆効果になることがあるので注意が必要です。
しっかり眠るために「食事」について意識したことはありますか? 「朝から体が重たい」 「夜中に胃がムカムカして起きてしまう」 「日中眠たい」 そんな悩みを抱えている方は「食事」に原因があるかもしれません。 私たち[…]
4.年齢や性別によって違う体温と睡眠の関係
これまでは一般的な体温リズムについて紹介してきましたが、年齢や性別によっても睡眠の特徴や取るべき対策が変化していきますので紹介していきます。
4-1.高齢者の睡眠の特徴
加齢とともに深部体温の変動が少なくなるだけでなく、深部体温そのものが低下してきます。
その為、高齢者特有な睡眠パターンの変化が表れてきます。
1. 深部体温の変動幅が小さくなる
若年層では、日中は深部体温が高く、夜間にかけてスムーズに低下します。
この深部体温の低下が「眠気」を誘導し、深い睡眠を促します。
しかし高齢になると、この体温の上下の差が小さくなり、夜間に深部体温があまり下がらなくなるのです。
その結果…
-
寝つきが悪くなる
-
夜間に眠りが浅くなる
-
早朝に目が覚めてしまう
などといった症状があらわれてきます。
2. 睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌が減る
深部体温を下げるホルモンの「メラトニン」は、加齢とともに分泌量が減少します。
メラトニンは、夜間に分泌されることで深部体温を下げ、入眠をサポートします。
高齢者ではこのホルモン分泌が少なくなり、体温がうまく下がらない為、睡眠に入りにくくなる傾向があります。
4-2.女性の睡眠の特徴とは?
女性における体温リズムの影響は月経・妊娠・更年期があります。
女性の体はホルモンの変動によって1ヶ月単位、人生単位で大きく変化します。
その中で、「体温リズム」と「睡眠」は非常に密接に関係しています。
1. 月経周期による体温の変動
女性の体温は月経周期によって大きく2つの時期に分かれます
| 時期 | ホルモン | 体温 | 睡眠への影響 |
|---|---|---|---|
| 低温期(生理後~排卵まで) | エストロゲン | 低め | 深部体温が下がりやすく、寝つきやすい・眠りが深い傾向 |
| 高温期(排卵後~次の生理まで) | プロゲステロン | 高め | 深部体温が下がりにくく、寝つきにくい・睡眠が浅くなりやすい |
【高温期の睡眠トラブル例】
-
「寝つきが悪い」
-
「夜中に目が覚める」
-
「なんとなく眠りが浅い」
⇒これは体温が高くて深部体温が下がりにくくなっているために起こりやすくなります。
2. 妊娠中の睡眠の特徴
妊娠すると、体温が高い状態による高温期が長い状態がしばらく続きます。
また、妊娠前のホルモンバランスの変化より大きな変化が起きる為、以下のような睡眠の問題が現れやすくなります。
妊娠初期〜中期
-
昼夜問わず強い眠気
-
深部体温が高くなることで寝苦しさや不眠を感じることが増える
妊娠後期
-
お腹の重みや頻尿などの影響で中途覚醒が増える
-
体温も高めに推移し、暑く感じることが多い
3. 更年期と体温・睡眠の変化
40代半ばから50代の女性が迎える更年期では、女性ホルモン(エストロゲン)の分泌が急激に減少します。
これにより、自律神経や体温調節機能が乱れやすくなり、以下のような睡眠トラブルが増加します。
【 更年期に見られる主な睡眠トラブル】
-
寝つきが悪い
-
眠ってもすぐに目が覚める
-
寝汗やホットフラッシュ(のぼせ・ほてり)で目が覚める
-
朝早く目が覚めてしまう
これらはホルモンの影響で体温リズムが乱れ、深部体温がスムーズに下がらないことが関係しています。
4.女性の体温リズムを整える快眠の工夫
上記でも睡眠の質をあげる体温調節の方法について取り上げましたが、女性特有の体温の変化のためにオススメな方法を紹介しておきます。
どれから行って良いかわからない方はまず以下の対策から初めてみてください。
高温期や妊娠中
-
寝る前の室温を少し涼しめ(26℃前後)に調整
-
吸湿・通気性のよい寝具やパジャマを選ぶ
-
寝る前にストレッチや腹式呼吸でリラックス
更年期世代
-
朝起きたら太陽の光を浴びて体内時計をリセット
-
日中に適度な運動をして、夜の自然な眠気を引き出す
-
湯たんぽや入浴で手足を温めて熱を逃がしやすくする
女性の睡眠は、体温リズムと女性ホルモンの影響を強く受けるため、年齢やライフステージによってさまざまな変化が現れます。
だからこそ、「眠れない=自分が悪い」と考えず、自分の体の変化に合った快眠環境を整えることが大切です。
ちょっとした工夫で、体温リズムが整い、睡眠の質がぐっと上がります。
「体の声」に耳を傾けながら、心地よい眠りを味方につけましょう。
4-3.子どもの睡眠の特徴とは?
成長期における睡眠は心身の成長にとても重要な役割を果たします。
子どもは寝るのが早く、朝もすっきり目覚めて元気なのが本来の姿です。
これは単に体力の差ではなく、体温リズムの働きが非常に活発だからなのです。
1. 子どもは体温のリズムが正確
子どもは、日中の活動で体温がしっかり上昇し、夜になると深部体温が大きく下がるという人間の理想的な体温リズムを持っています。
この深部体温の変化こそが、自然で深い眠りを誘導する重要ポイントです。
大人になると様々な原因によりこの深部体温の調整が上手くいかなくなり不眠になっていきます。
【子どもの体温変動の特徴】
-
日中
活動的で深部体温が高く保たれる -
夜間
体温がスムーズに下がり、眠気が強くなる -
睡眠中
深いノンレム睡眠が長く続き、成長ホルモンがしっかり分泌される
2. 子どもの睡眠が理想な理由
深部体温が適度に下がることで、ノンレム睡眠(深い眠り)の時間が長く確保されます。
この時間帯には、「成長ホルモン」が多く分泌されるため、心身の発達にとても重要な役割を果たしています。
また、子どもは深い眠りについていることが多いので睡眠中に夜中目が覚めることが少なく、連続した深い眠りを維持しやすいのも特徴です。
3. 子どもの睡眠リズムが乱れやすい要因
しかし、昔と違い学校帰りに子供同士で公園で遊ぶ機会も減り、塾に習い事、帰ってきて宿題、長時間のゲームと言ったように夜9時に就寝する子供は減り、遅くまで寝れない子供が増えました。
その影響で子どもでも睡眠リズムが乱れるケースが増えています。
以下のような生活習慣は、体温リズムの乱れ、睡眠の質を下げる原因になるので子供の将来を考えると親も意識的に状況を把握すべきだと感じます。
【子供の睡眠の質を下げる原因】
- 眠る直前までのスマホやテレビ
→ 強い光が脳を刺激し、深部体温の低下を妨げる - 夜遅くまでの活動や夜ふかし
→ 体温がうまく下がらず、眠気のタイミングを逃す。 - カーテンを開けず朝日を浴びるない
→ 体内時計がリセットされず、体温のリズムがずれる。
子どもの快眠を促す体温調節のコツ
昔は放課後公園に行き外で鬼ごっこや遊具で遊んでいた子供たちも今や外にいてもスマホやポータブルゲーム機でオンライン対戦
運動する子供としない子供は二極化していると感じています。
子どもだからといって何もしなくてよいわけでなく、スマホの使用や運動量の少ない子供たちは意識的に生活習慣を見直す必要があると私は思っています。
健やかな眠りのためには、体温リズムを自然に整える環境づくりが大切です。
- 就寝前の入浴を活用する
寝る1~2時間前にぬるめのお風呂(38〜40℃)に入ることで、体温を一度上げて、自然な低下を促します。 - 寝る前は静かな時間を過ごす
子供の場合楽しいことがあるとテンションが上がってはしゃぎがち、
元気が良いのはいいことですが、興奮して寝つきが悪くなってしまいます。
寝る前は絵本の読み聞かせやリラックスできる音楽などで、脳と体の「クールダウン」をしてから就寝するのがベストです。 - 寝室の温度はやや低めに保つ
子供の体温は親より高く、室温が低いと風邪ひかせてはいけないと思い上げ過ぎると寝つきが悪くなります。
布団をかけて丁度よくなるようにすることで深部体温が下がりやすくなり、入眠がスムーズになります
(夏:26〜27℃、冬:18〜20℃が目安)。 - 朝起きたらカーテンを開けて朝日を浴びる
朝に弱い子供が最近増えたように思います。
体質や夜更かしによるものもあるかと思いますが、カーテンの性能がよくなり光を通しにくい素材のものも増えたことで朝になっても部屋が真っ暗といった家も少なくないのではないでしょうか?ベッドはカーテンの近くに置き目が覚めたらすぐにカーテンを開けて外の日差しを取り入れる工夫が必要です。
そうすることで体内時計がリセットされ、1日の体温リズムがスタートします。
「また眠れなかった…」そんな夜を何度もくり返していませんか? 布団に入っても目が冴えてなかなか眠れない。 ようやく寝たと思ったら、夜中に何度も目が覚める。 朝やっとの思いで目を覚ますもスッキリしない。 […]
子どもの成長の為に質の高い睡眠を!
深部体温がしっかり下がることで深く、成長に必要な質の高い眠りが得られています。
しかし、現代社会の子どもたちはとにかく忙しく授業時間の延長に塾に習い事、皆平等に与えられた時間の中で睡眠を削って生活している子供たちも多くみられます。その影響で睡眠のリズムが乱れてしまう事があります
その為睡眠時間を取れず育った子供たちは低身長というデータも出ています。
だからこそ、以下のようなサポートがとても重要です。
-
規則正しい生活習慣
-
寝る前の穏やかな時間の確保
-
朝・昼・夜の体温リズムを意識した工夫
体温リズムを味方につけて、子どもたちの睡眠をしっかり守り、心と体の健康を育んでいきましょう。
体温変化が大きく、夜にしっかり深部体温が下がるため、眠りも深くなります。
子供の今ではなく未来の為に睡眠の特徴を理解して、自分に合った体温調節法を見つけましょう。
まとめ:ぐっすり眠るには、体温リズム
ぐっすり眠るには体温リズムを整える事が大切です。
「なんだか最近眠れないな…」と思ったら、ぜひ体温に目を向けてみてください。
- 深部体温を緩やかに下げること
- 皮膚温を上げて熱を逃がすこと
この2つが、快眠への大きな鍵となります。
これまで述べてきた生活習慣や寝室環境を少し見直すだけでも、眠りの質は大きく変わります。
心と体がしっかり休まるバランスの良い睡眠を手に入れて、翌朝の目覚めをもっと心地よいものにしていきましょう!
マッチ鍼灸整骨院で睡眠障害・不眠を解消!
 当院では、睡眠の問題に特化した鍼灸整体施術で早期改善を目指します。
当院では、睡眠の問題に特化した鍼灸整体施術で早期改善を目指します。
- 鍼灸治療: 経絡を整え身体の内側から血流を促進、痛みや痺れを改善します。
- 整体・骨盤矯正: 骨盤や腰椎の歪みを整え、身体の外側から痛みや痺れを改善します。
- 再発予防トレーニング: 快適に眠れる体つくりをサポートします
- オーダーメイドの治療プラン: 一人ひとりの症状や生活スタイルに合わせた治療プランを提案します。
起床、就寝時に倦怠感や寝れないといった場合は早めの対応が肝心です。 「我慢できるから大丈夫」と思っている状態はずでに身体の状態はかなり悪くなっています。
少しでも気になる症状がある場合は、お気軽にご相談ください。
マッチ鍼灸整骨院が、症状の改善から予防まで全力でサポートします!
早めの治療で、快適な毎日を取り戻しましょう!